尿路・性器感染症
尿路・性器感染症
膀胱炎
膀胱炎膀胱炎は、腸内細菌が尿道から入り膀胱で増殖して起こる病気です。腸内細菌は、大腸・直腸にすんでいる菌ですので、肛門やその周囲には必ず存在します。排尿痛、残尿感、頻尿などが、膀胱炎の特徴的な症状です。膀胱粘膜の炎症で、血尿が出ることもあります。
膀胱炎では熱はでません。熱がある時は、細菌が腎臓まで上り腎盂腎炎(詳しくは下記)を起こしていると思われます。早めに抗菌剤による治療が必要です。
再発を繰り返す人は、治りきっていないうちに薬をやめてしまっているのかもしれません。または、膀胱炎になりやすい生活習慣が原因になっている可能性もあります。専門医での精査が必要です。
慢性化すると、間質性膀胱炎(詳しくは別ページ)になるおそれもあります。
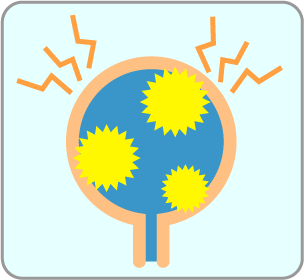
腎盂腎炎
細菌が、腎盂、腎杯、腎実質に及んだ感染症を腎盂腎炎と言います。典型的な症状は発熱、背部痛を認めます。発熱は悪寒戦慄を伴い、悪心、嘔吐などの消化器症状を伴い、全身倦怠感が強いことも特徴です。女性に多く、男性は稀な疾患です。基礎疾患がない場合は、抗菌剤治療に良く反応します。
精巣上体炎
精巣に付属する精巣上体と呼ばれる組織に、急性の炎症がおこる病気で、陰嚢が腫れて痛みがあり、高熱が出ます。細菌が尿道から入って、前立腺、精管を通って精巣上体に感染しておこることが多く、発熱と、陰嚢の腫れ、痛みから診断されます。
治療としては、細菌に効く抗生物質を用い、陰嚢部の冷湿布によって痛みは改善します。熱は5~6日でとれますが、しこりがとれるには2~3か月かかることもあります。
尿道炎
尿道に炎症がおこって、排尿時に痛んだり、膿が出たりするのが尿道炎です。尿道炎の大部分は細菌の増殖によっておこります。その代表が淋菌とクラミジアです。尿道炎の症状は、排尿痛と尿道からの分泌物です。
-
淋菌性尿道炎
潜伏期は短く、1週間程度です。分泌物は多量、膿様で、尿道口に付着しても白色か黄色に見えます。排尿後に、尿道に疼痛を感じます。
-
クラミジア尿道炎
排尿痛、分泌物の自覚症状が軽く、潜伏期は2~3週間です。尿道分泌物は少量、透明で、排尿後に外尿道口に尿がついているのと区別できません。排尿痛も軽くて、疼痛というより、いつもとちがう感じが自覚される程度で、気づかない場合もあります。若い人の尿道炎は大部分が、淋菌かクラミジア、またはその両方が発見されますが、どちらも発見できない尿道炎があります。原因菌が正確に確定されれば、治療は1~2週間の服薬で治ります。
淋菌、クラミジアの感染は、必ず感染源があります。また感染源以外に自分が感染させたパートナーが別にいる場合もあります。淋菌、クラミジアはいったん治っても機会があれば感染をくり返します。パートナーを放置すれば再感染の危険があるので、いっしょに診断、治療を受けることが必要です。
急性前立腺炎
悪寒戦慄を伴う高熱、倦怠感、排尿痛、会陰、陰嚢などの陰部を中心とした疼痛や排尿痛などの症状を認めます。尿道から逆行性や血液から腸内細菌が前立腺に感染して発症するとされています。
治療は抗菌剤の投与が基本で、高熱を伴う場会は、入院の上、点滴治療を行うこともあります。抗菌剤の投与期間は4週間程度が一般的です。
亀頭包皮炎
小児のおちんちんの痛みや腫脹で受診されます。抗菌剤軟膏で改善する場合が多いのですが、包皮の中に膿が溜っている場合は排膿が必要となります。包茎を合併していることがしばしば見られます。

